協力業者・傭車を使っているトラック運送事業者様へ
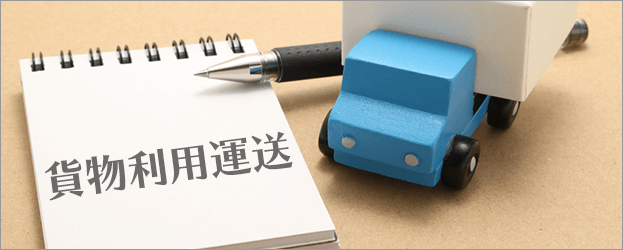
一般貨物の許可を取得されている運送会社が、自社のトラックが空いていないときや自社トラックでは取り扱えない貨物量や大きさであるときは、別の一般貨物の許可を取得されている運送会社に外注に出すことがあります。
このことは、「傭車(ようしゃ)」とも呼ばれます。
外部のトラック運送会社に自社の荷主の貨物をお願いするためには、仕事を依頼する(発注者)側の運送業者は、貨物自動車利用運送の資格が必要になります。
トラックを使った「利用運送」の資格と言うと「第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)」の登録を思い浮かべる運送会社さんもいらっしゃいますが、貨物自動車利用運送と第一種貨物利用運送事業とはまた別のものです。
法律的なことを言いますと、貨物自動車利用運送は貨物自動車運送事業法に基づく運送形態であり、第一種貨物利用運送事業は貨物利用運送事業法に基づく事業形態になります。
トラック運送会社が、一般貨物の許可を取得している運送会社、つまり緑ナンバーがついた自社トラックを運行している運送会社に傭車を依頼する時は、一般貨物自動車運送事業の許可の中で行うことになります。第一種貨物利用運送事業の登録は不要です。
一般貨物自動車運送事業者さんが第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)の登録が必要になるケースは、利用する運送会社(外注先)が、第一種貨物利用運送事業者(いわゆる水屋)の場合になります。
全ての一般貨物自動車運送事業者さんが、無条件で貨物自動車利用運送を行えるわけではありません。
一般貨物自動車運送事業者さんが貨物自動車利用運送を行えるのは、事業計画の貨物自動車利用運送を「する」の状態になっている必要があります。

言い換えると、一般貨物の許可を取得した際、事業計画が『貨物自動車利用運送をする』になっていればよいのですが、『貨物利用運送をしない』となっている事業計画で許可を取得している場合は、貨物自動車利用運送を行うための事業計画の変更認可申請手続きを行う必要があります。
決算書に傭車代が費用として計上されているのに貨物自動車利用運送の資格(認可)を取得していない運送会社さんは、今すぐに、事業計画に利用運送をするための変更認可申請手続きが必要になります。
というのは、貨物自動車利用運送の資格を持たずに庸車を使うことは違法であり、巡回指導で指摘されたり、監査の場合は、事業計画変更認可違反として行政処分の対象となってしまうからです。
この行政処分の内容は、貨物利用運送を行うか否かの項目への違反として、初違反の場合は10日車、再違反の場合は20日車の処分日車と定められています。
貨物自動車利用運送を行うための行政手続きは、始める前に申請し、運輸局より認可を取得しなければなりません。
申請書を提出してから運輸局での審査を経て認可を取得するまでに4か月程度の期間を要することが多いです。
貨物量が自社の車両だけで対応することにそろそろ限界が来ていて、協力会社さんに傭車を出そうとお考えのトラック運送会社さんは、貨物自動車利用運送を行うための変更認可申請手続きの準備を進めましょう。
サービス内容
行政書士法人シグマでは、これから貨物自動車利用運送を行われる一般貨物自動車運送事業者さんのために、事業計画変更認可申請手続きのサポートを行っております。
協力業者さんが見つかった、傭車を依頼したいとお考えのトラック運送会社様はご相談ください。
また、巡回指導や監査で、貨物自動車利用運送の認可を速やかに取得するよう指導を受けられた事業者さんからのご依頼も承っております。
事業計画変更認可申請サポートサービス内容
| 変更認可要件の調査 | ○ |
| 認可申請書類の作成 | ○ |
| 利用する事業者との運送に関する契約書のひな形提供 | ○ |
| 変更認可申請書の提出代行 | ○ |
| 認可書の受領代行 | ○ |
料金のご案内
| 業務 | 料金(税込) |
| 一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更認可申請(利用する運送会社の数:3社以内) | 110,000円~ |
料金はシグマの報酬額であり、交通費、郵送費などの実費は別途必要となりますのでご了承ください。
貨物自動車利用運送を始めるための変更認可申請手続きの流れ
- お問合せ
- ご相談
- お見積
- 正式なご依頼、手続き費用のご入金
- 変更認可要件の調査・確認
- 必要書類の収集・作成
- 運輸局へ変更認可申請書類の提出
- 審査
- 認可書の受領
- 貨物自動車利用運送のスタート
貨物自動車利用運送を始めるまでに必要な日数
まず、運輸局での審査だけでも概ね4か月の期間を要します。
そして、変更認可申請書には、協力会社(傭車先)との間で締結した運送委託契約書の提出が必要になるため、この契約書の締結に日数を要している運送会社さんが多いようにお見受けします。
少しでも早く協力業者に外注したいトラック運送会社さんは、運輸局での審査期間は短縮することは現実的にできないため、運送委託契約書をどれくらい早く協力業者との間で締結できるかがポイントになると思います。
協力業者さんがに法務部があるような規模の大きい運送会社さんの場合は、法務部でのリーガルチェックや調印手続きで日数を要することが多いです。
お打合せ時にご準備いただきたい書類
シグマに、貨物自動車利用運送を始めるための変更認可申請をご相談・ご依頼いただく際には、下記の書類をご準備いただけると、スムーズに手続きを進めることが可能になります。
- 貴社の一般貨物自動車運送事業の許可書(コピー)
- 貴社の事業計画がわかる許可申請書類(コピー)
- 協力業者(傭車先)の会社名・本店所在地がわかる書類
なお、協力業者(傭車先)の情報が不正確な変更認可申請書類を提出すると、運輸局での申請書類に補正が発生し、審査が中断してしまいます。
審査が中断してしまうと、その中断期間の分だけ認可が下りるまでの期間が伸びてしまいます。
運輸局での審査を円滑に進めるためには、認可申請書類の精度をどこまで上げられるかが勝負だと言えるでしょう。
また、すでに協力業者さんと運送委託契約書を締結している場合は、その契約書のコピーをご準備いただけますとより具体的な打合せを行うことが可能になります。
貨物自動車利用運送の認可を取得したら
貨物自動車利用運送の認可取得後、協力業者(傭車先)が増えたり・減ったりした場合は、変更届出手続きが必要になります。
また、毎年7月10日が提出期限となっている実績報告書には、協力業者(傭車先)の車両で運んだ貨物量(輸送トン数)を記載する欄があります。
自社の車両で運んだトン数と協力業者に依頼したトン数を分けて社内で管理をしておくと、実績報告書作成の際に手間と時間を節約することができますのでお勧めです。
貨物自動車利用運送の認可取得手続きでお困りごと、ご不安なことがございましたら、行政書士法人シグマまでお問合せください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
















