監査や巡回指導の対応について
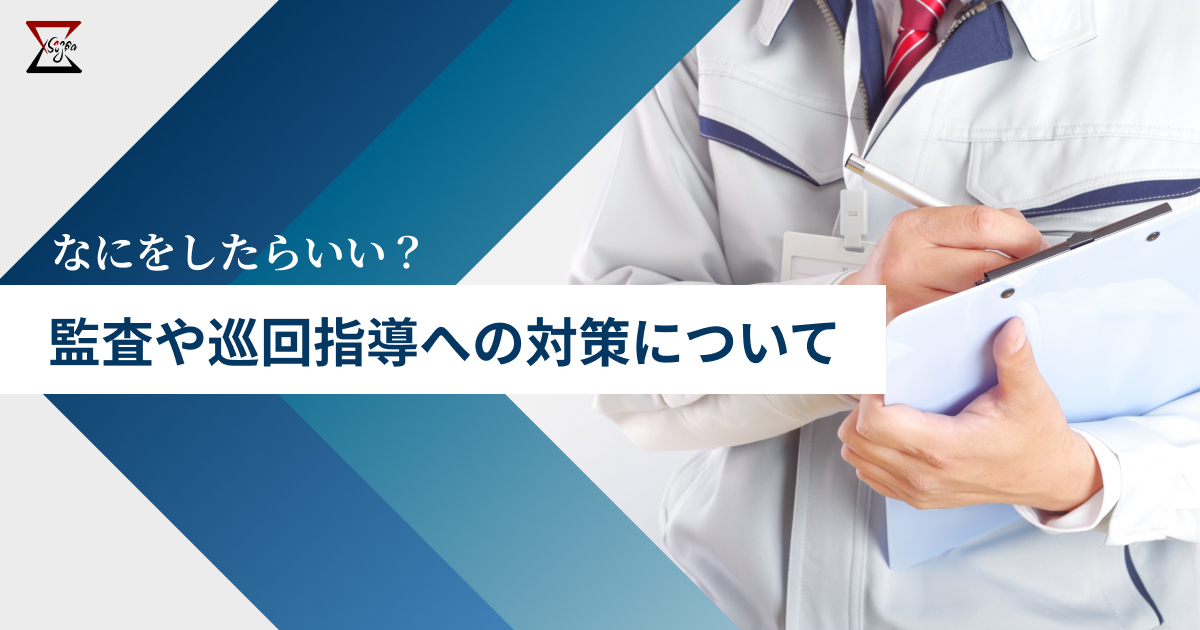
先生!!トラック協会から巡回指導に来るという郵便が届いたのですが・・・。どうしたらいいでしょうか?
慌てなくても大丈夫ですよ。まずは、落ち着きましょう。
まずは巡回指導日時はいつかを確認しましょう。
そして、巡回指導当日に準備しなければならない書類が何月分のものなのかも把握しましょう。
通知文のどこかに記載されています。
そして、指導項目や準備書類の一覧表がトラック協会からの郵送物に入っていればそれを使用して自己チェックをしみてください。
もし入っていないようでしたら、こちらで用意した自己チェックシートをお送りしますよ。
今ざっと目を通してみましたが、心配な項目がいくつかあります。
それでは巡回指導当日までの間に一緒に不安点を解消するために対応を考えていきましょう。
運送業(一般貨物自動車運送事業)を行っている方の中には、運輸局が実施する「監査」やトラック協会が実施する「巡回指導」に不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
たしかに監査や巡回指導は「面倒な事」なのですが、面倒だからと言って気にしないでいると、大きなリスクを負うことになります。
巡回指導でE判定となってしまい、指摘事項を放置したままにしておくと、増車や車庫の拡張、営業所新設といった事業規模拡大ができなくなり、事業運営の足かせになってしまいます。
さらに、巡回指導でD判定及びE判定となってしまうと、重点事業者となってしまい、半年毎に巡回指導が行われることになってしまいます。
また、運輸局が実施する監査では、法令順守に問題があるとされた場合には改善報告を行うともに、行政処分としてナンバーを取り上げられて車両が使用できない期間が生じてしまったり、悪質だと判断された場合には、営業停止処分や、最悪のケースでは許可の取消しという可能性すらゼロではありません。
さらに、行政処分を受けてしまうと公表されてしまうため、取引先にも行政処分を受けた事実は知られてしまいます。
とはいえ、シグマにご相談いただく方の中にも、「そうは言っても何をすればいいのかわからない」という方が多くいらっしゃいます。
そのような方のために、この記事では、巡回指導や監査の概要と、どのような対策が必要になるのかを説明しています。
Contents
監査と巡回指導
運送業許可を取得したあとには、営業所に監査官、指導員と呼ばれる外部の方が来て、営業実態について色々と調査される機会があります。
国土交通省(運輸局や運輸支局)による「監査」と、トラック協会に設置された地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による「巡回指導」です。
巡回指導は、運輸開始後1か月~3ヶ月以内に通常実施され、初回の巡回指導でA判定を取得した運送会社に対しては2~3年に1度のペースで行われます。
巡回指導日の実施案内は、2~3週間前に、営業所宛てに郵便にて、「いつ来るか」「何を用意しておけばよいか」などの通知があり、巡回指導を実施した結果、違反事項があれば指導という形で改善を求められます。
監査は、重大事故を起こしたときや、巡回指導によって悪質な法令違反が発見されたとき、最近は法令違反の疑いがあるという通報があったときや、長期間監査を実施していない場合などに行われます。
監査の実施方法は、事前に通知がある場合もあれば、営業所に監査官が突然来る場合もあります。日時が指定されて運輸局の窓口に呼び出しを受けることもあります。監査の進め方は監査官の意向で決まります。
監査は、巡回指導とは違い、基本的には突然、実施されると考えた方がよいでしょう。
巡回指導は通常2時間~3時間程度で終わりますが、監査にいたっては違反項目が見つかると1日では終わらず、複数日にわたり監査官が納得するまで行われることもよくあります。
監査が実施された場合、違反事項があれば、違反の程度によって行政処分を受けることになってしまいます。
巡回指導のポイント

ここでは、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導のチェックポイントを紹介します。
なお、重点事項とされているものは太字、最重点事項とされているものは赤太字にしてあります。
かなり細かいところまでチェックを受けるということがおわかりになるのではないでしょうか。
運行管理に関する部分に項目が多く、かつ重点項目が多いのが特徴です。
事業計画等
- 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
- 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
- 自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
- 乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
- 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
- 届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)
- 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
- 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
帳票類の整備、報告等
- 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
- 自動車事故報告書を提出しているか。
- 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
- 車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。
- 営業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)
運行管理等
- 運行管理規程が定められているか。
- 運行管理者が選任され、届出されているか。
- 運行管理者に所定の研修を受けさせているか。
- 事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
- 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
- 過積載による運送を行っていないか。
- 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
- 乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
- 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
- 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
- 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
- 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
- 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
車両管理等
- 整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。
- 整備管理者が選任され、届出されているか。
- 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
- 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
- 定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
労基法等
- 就業規則が制定され、届出されているか。
- 36協定が締結され、届出されているか。
- 労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)
- 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
法定福利
- 労災保険・雇用保険に加入しているか。
- 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
運輸安全マネジメント
- 輸送の安全に関する基本的な方針が定められているか。
- 輸送の安全に関する目標が定められているか
- 輸送の安全に関する計画が策定されているか
- 運輸マネジメントの公表がなされているか
このようなチェックポイントについて、太字、赤太字の項目を中心に調査されることになります。
昨今は、健康起因事故防止に向けて、運転者に法定の健康診断を受診させているかのチェックも厳しくなってきています。
書類の準備に不安がある場合は、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関に問合せをして、巡回指導当日に向けて帳票類をしっかり準備するのが、巡回指導を乗り切るポイントと言えるでしょう。
巡回指導の結果、改善が必要な点については改善するように指導を受けます。
ただし、あまりにも悪質な場合や、指導を無視し続けたりした場合などには、運輸支局に通報され、監査が行われるきっかけになることもありますので、日頃からいつ巡回指導が来ても良いような準備をしておけるのがベストです。
ですので、法令遵守体制に自信のない運送事業者様は、巡回指導を良いチャンスとして、少しずつ改善していくというのが賢いやり方ではないかと思います。
事業拡大を考えている方は更に注意が必要です
なお、2019年11月から、事業規模の拡大となる事業計画の変更認可申請の際の要件に、巡回指導による総合評価に関する基準が設けられました。
この「事業規模の拡大」とは、車庫の拡張や営業所の新設、増車が該当します。
増車に関しては、申請日前3カ月間または申請日以降に、変更認可申請をする営業所(※)の巡回指導の結果で、総合評価が「E」評価になってしまうと、その巡回指導で指摘を受けた全ての項目についての改善報告を行っていない場合は、増車手続きは事業計画の変更認可扱いとなり、運輸局へ申請しても認可を受けることができないため、増車できないということになってしまいます。
※営業所の新設を行う場合にあっては申請地を管轄する地方運輸局内におけるすべての営業所
このように巡回指導で悪い評価になってしまうと、事業拡大が停滞してしまい、最終的に荷主さんに迷惑をかけてしまうことになってしまうのです。
D判定・E判定の場合は、次の巡回指導までの期間が短くなります
巡回指導で指摘事項がある場合、いつまでに改善報告を行うよう巡回指導員から指示があります。
D判定又はE判定の場合は改善報告を終えたら終わりではなく、6か月後に、再度巡回指導が行われます。
再度の巡回指導では、改善報告を行った内容が問題ないかの確認を含めて、法令遵守体制に問題ないかという観点で帳票類の確認があります。
巡回指導でD判定又はE判定となった場合は、6か月後の再度の巡回指導までしっかり対応する必要があると言えるでしょう。
監査のポイント
運輸支局の行う監査には3つの種類があります。
- 特別監査
- 一般監査
- 街頭監査
特別監査は「トッカン」とも呼ばれ、重大事故や重大な法令違反があった際に行われる監査です。運送業界の方であれば聞いたことのある方も多いのではないのでしょうか。
監査は前述のとおり「臨店」と言われる営業所や車庫で行われるものと、代表者などが呼び出されて行われるという2つのパターンがあります。
呼出監査は、代表者や運行管理者が運輸局または運輸支局に呼び出されて、書類を見せたりヒアリングを受けたりするもので、臨店しなくても確認できるような事項についての監査や、監査を受けた後の改善状況の報告をするときに行われます。
ちなみに、呼出監査の通知を無視していると、臨店監査を受けることになってしまうこともありますので、呼び出しにはきちんと応じた方が行政処分は軽く済む可能性が高いです。
監査での重点事項は以下のようなものです。
- 事業計画の遵守状況
- 運賃・料金の収受状況
- 損害賠償責任保険(共済)の加入状況
- 自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無
- 社会保険等の加入状況
- 賃金の支払状況
- 運行管理の実施状況
- 整備管理の実施状況
見比べてもらうとわかる通り、巡回指導とほぼ同じ内容になっています。
運行管理の実施状況で補足するならば、健康起因事故防止のため運転者の健康診断の受診状況や、トラック運転手の飲酒運転が社会問題となったため点呼執行体制についてより厳しく確認される事業者様が多い印象があります。
しかし巡回指導と違い、違反事項が見つかった場合には行政処分として車両の使用停止処分などを受ける可能性があります。
しかも無通知で突然入るため、日頃からの法令順守がより一層大切になってきます。
車両の使用停止処分については、一般社団法人運輸安全総研トラバスのブログ「行政処分での車両停止の対象車両の決め方やナンバープレートが外されてしまう場合の手続きの流れ」もご参照ください。
Gマークを取得していると監査の頻度が減る可能性がありますので、自社の法令順守にしっかりと取り組もうというトラック運送業者様は、Gマークの取得を検討するのも良いかもしれません。
行政書士法人シグマでは、Gマークの取得に関してもご相談を受け付けていますので、Gマーク取得サポートのご依頼、ご相談もお気軽にご連絡ください。
対策の基本は法令順守

監査や巡回指導の目的は、法令上では事故防止と運輸の適正化ということになっていますが、わかりやすく言ってしまえば「ルールを守っているか?」ということを確認することです。
しかし、「法令順守」と言葉で言うのは簡単ですが、法令を順守しながら運送業を行っていくためには、非常に数多くのルールを守らなければなりませんので、実際に運送業をしながら法令順守をするのはそれほど簡単なことではありません。
そういった事情もあり、なかなかしっかりと法令順守できていない事業者様が多いのも事実です。
だからと言って、法令違反をしたままで日々の運行を行っていると、実際に監査や巡回指導が入るというときに大慌てするということになりかねません。
実際にシグマにも、「巡回指導日の郵便が届いたが、帳票類がちゃんとできているかわからなくて不安」「監査が行われて行政処分を受けてしまった、改善方法を一緒に考えて欲しい」といったような相談があります。
さきほど紹介したとおり、監査や巡回指導でのチェック項目は多岐にわたります。
短期間で是正しようと思うとかなり大変ですし、過去に遡ってデータを確認して書類を作ったりするのは間違いも発生しやすいです。
だからといって、実態と異なる書類、つまり虚偽の書類を作成するのは、最悪の監査対策です。百戦錬磨の監査官や指導員の目を誤魔化すことは難しいです。
監査に関しては、記録の改ざん・不実記載を行いそれが見つかると、その行為自体に対して行政処分の対象となります。
| 違反行為 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| 点検整備記録簿の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
| 点呼記録簿の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
| 運行記録計の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
| 運転日報の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
| 教育記録簿の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
また、監査は基本無通告で入りますので、そのまま行政処分を受けるということになってしまえば、荷主、金融機関や社会からの信頼を損ない、最悪な場合、事業の継続自体も危うくなります。
したがって、最も確実な対策というのは、いつ監査や巡回指導が入っても大丈夫なように、日々しっかりと法令順守をしながら事業を行うということです。
確かに非常に大変なことなのですが、後になってまとめて膨大な作業をしなければならないことを考えれば、日々しっかりと書類を作ったり、点呼をしたり、必要な手続きをしたりすることが、結局は一番楽ですし経営上のリスクも小さいです。
法令順守ができていない事業者様は、悪意があってルールを破っているわけではなく、日々の業務の中で、「しっかりやらないといけないな」とは思いながらもなかなかそこまで手が回らないというケースがほとんどだと思います。
行政書士法人シグマでは、法令順守を維持したいという事業者様の法令順守のサポート、監査および巡回指導対策のサポートを行っています。
法令遵守体制を確実に構築したいとお考えの運送会社様には、顧問契約をお勧めしております。
契約内容によりますが、原則、月1回営業所に担当行政書士が伺い、帳票類の確認や事業運営上のお悩みを伺わせていただくというのが、基本的な顧問契約の内容です。
さらに運送業の専門家集団である一般社団法人運輸安全総研トラバスによる、様々なサービスも提供しています。
法令遵守体制を構築して、健全に発展する事業展開をしたいとお考えのトラック運送業者様は、行政書士法人シグマまで、ぜひ一度ご相談ください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.

















