運送業許可を取れない人は?
トラック運送業の許可を取りたいのですが、以前いた勤務していた運送会社では、車両停止の行政処分を受けていたことがあります。
こういった場合でも許可は取れるのでしょうか?
以前いた会社が処分を受けた日や、そのときの立場などによって変わってきますが、許可を受けられない可能性もありますね。
許可が受けられないのは困りますね。
具体的にはどういった場合に許可が受けられないんですか?
法律や国交省の公示している基準など、いくつかのルールがありますので、それに当てはまってしまっていないか確認してみましょう。
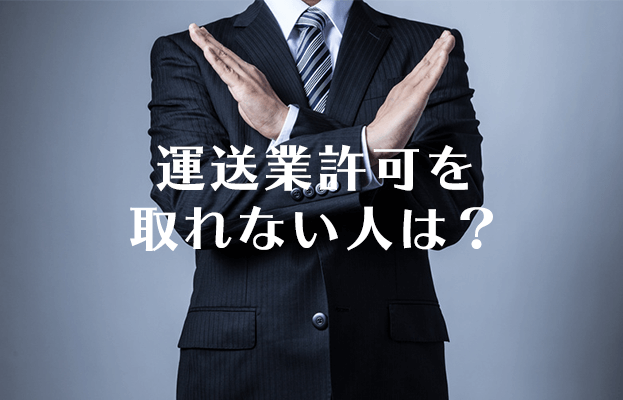
緑ナンバーをつけてトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)を行うためには運送業の許可を取る必要がありますが、残念ながら許可を受けることができない人がいます。
この記事では、運送業許可申請の前提として、どのような人・会社は許可を受けることができないのかについて解説します。
欠格事由
運送業についてのルールが書かれている貨物自動車運送事業法には、許可を受けることができない人が定められています。
貨物自動車運送事業法に定められている一般貨物の許可を受けられない人の条件(欠格事由)は次の8つです。
以下どれかひとつにでも該当する人は一般貨物の許可を受けることができません。
- 許可申請者が1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 許可申請者が一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
- 許可申請者と密接な関係を有する者(親会社、子会社、グループ会社など)が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可申請者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分の係る聴聞の通知が到達した日からその許可取消し処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの
- 許可申請者が、監査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分の係る聴聞の通知が到達した日からその許可取消し処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に事業廃止の届出があった場合に、許可申請者が聴聞の通知が到達した日前60日以内に事業廃止した法人の役員であった者で、事業廃止の届出日から5年を経過しないもの(事業廃止に相当の理由がある場合を除く)
- 許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合において、その法定代理人が上記の1.~2.及び4.~6.並びに下記8.いずれかに該当するもの
- 許可申請者が法人である場合、その役員が上記1.~2.及び4.~7.のいずれかに該当する者があるとき
少しわかりにくいものもあるので簡単に補足します。
2.の「法人の役員」についてですが、これは登記上の役員だけではなく、実質的に役員と同じかそれ以上の職権や支配力を持っている人も含みます。
これは上記の6.と8.の「役員」でも同じです。
また、7.には「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」とありますが馴染みのない表現ですよね。
この前提には、法定代理人(多くの場合は親です。)が未成年者に対して、運送業に関する営業を許可していれば、法律上は成年者と同様に取り扱われるという法律があります。
また、結婚している未成年者も、法律上は成年者と同様に取り扱われます。
したがって、この7.のルールは、「法定代理人からの許可を得ていない未婚の未成年者または成年後見人が運送業許可の申請をするときには、法定代理人について欠格事由を判断しますよ。」ということです。
8.については、役員(実質的に役員と同じかそれ以上の職権や支配力を持っている人も含みます。)の中に1.~2.及び4.~7.の事項に1人でもに該当する人がいた場合には許可が受けられない点に注意が必要です。
国交省の処理方針
欠格事由
さきほど紹介した法律上の欠格事由の他に、関東運輸局長が公示している関東運輸局管内の運送業の許可申請の処理方針にも以下のような欠格事由が存在しています。
申請者または申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員が、貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)または申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
その他法令順守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
これについても簡単に補足していきます。
上記の「役員」には、法律に定められた欠格事由のときと同じように、実質的に役員と同じかそれ以上の職権や支配力を持っている人も含みます。この「役員」には常勤役員の他に、非常勤役員や会社法上の役員には該当しませんが、顧問のような肩書の方も含まれますのでご注意ください。
次に「悪質な違反」については、許可申請の処理方針の細部取扱いについて以下の3項目が掲げられております。
- 違反事実もしくはこれを証するものを隠滅し、または隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合
- 飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為または社会的影響のある事故を引き起こした場合
- 事業停止処分の場合
また、最後に書かれている「自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者」の中には、処分を受けた会社の、処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する役員だった者を含みます。
したがって「会社が自動車の使用停止処分を受けてしまったから、別の会社を作って許可を受けよう」というやり方はできないことになります。
社会保険の加入
運送業の許可を受ける際には、「健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること」も必要になります。
トラック運送業を経営するための一般貨物自動車運送事業の経営許可申請する場合には、法人でも個人事業でも、原則として社会保険、労働保険の加入義務がありますので、「社会保険に加入しなければ運送業許可は取れない」と考えて問題ありません。社会保険に加入しないと、運輸開始後の巡回指導で指摘事項になったり、監査時に発覚してしまうと、行政処分の対象になってしまいます。それでは、社会保険の加入に対しては、運輸行政は厳しい目を向けています。
少し補足しておきますと、個人事業主の場合には、使用労働者数が1~4名であれば労働保険のみでOKですが、ドライバーさんを5名雇うと社会保険も加入する必要があります。より詳しい社会保険の内容は、顧問社労士さんや、年金事務所、労基署など行政機関にご確認ください。
運輸開始前の確認報告を行う際、社会保険への加入状況を報告する(社会保険の新規適用届と労働保険の関係成立届の写しを提出する)必要があります。それまでには社会保険への加入手続きを進めておきましょう。社会保険に加入していないと運輸開始前の確認報告が行えずに、事業用ナンバー取得の際に必要となる事業用自動車等連絡書が受け取れなくなってしまいます。
おわりに
この記事で紹介した事項は、「これに該当すると許可が受けられない」という許可申請の前提となる部分ですので、特に事前のチェックが大切になります。
営業所や車庫を借りてしまってから、このような事項が発覚してしまうと、まとまった額の損失が生じる可能性も高いので、慎重に確認しておきましょう。
行政書士法人シグマにご依頼いただいた場合には、このような事項に該当しないかを依頼者様にヒアリングしたり、社会保険の専門家である社会保険労務士を紹介するなど、事前の準備もサポートしております。
トラック運送業の許可申請で不安をお持ちの方は、お気軽に一度ご相談ください。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。なお、報酬額のお見積もりは、面談(対面もしくはオンライン)にて詳しいお話をお聞きしてからのご提示となりますので、ご了承ください。
お問い合わせには、必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている
- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている
- 返信メールが受信できない設定になっている
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。
※We are very sorry, but we are available only in Japanese language.
















